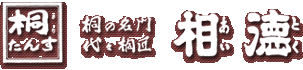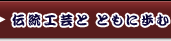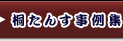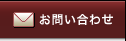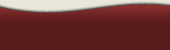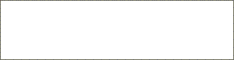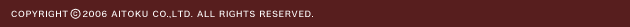老舗風土記 第五回

★職人不足の心配なし★
★桐箪笥の名門「相徳」は、
戦前には宮家、家族等の上流階級に製品を納め、大いに評判をとった。
それらの納入品を店頭に飾った写真が掲げてある。
ずらりと並んだ商品の中にいて、すこしも息苦しさを感じず、
さっぱりとした気分なのは、桐という素材の端正な木肌のためと、
箪笥という器物がシンプルにできているからだろう。
模様をつける箪笥もあるが、それは特殊なもので、
普通は引き手の金具を取り付けるだけである。
必要性だけでこれほど美的に作られている桐箪笥は、
無垢な娘さんが嫁入り道具にするのにぴったりである。
桐たんすの値段は、二十万円から百三十万円というところである。
桐材が湿気を防ぐことは前に記したが、
桧、杉、松その他の木材のように、匂いを出さないことも、
収納器の素材として適しているという。
大事なものに木の香がうつるのはよくない。
木の香がうつってよいのは、樽酒と風呂桶ぐらいだろうか。
箪笥以外の収納品として、美術館や図書館から箱の注文がある。
書画、古文書等を保管するためである。
近頃ではテープの収納にも桐箱が利用される。
カメラも桐箱の保管するのがよいという。
話はあちこちに飛ぶが、桐たんすの再生(削り直し)が盛んになり、
脱サラの職人が出てきた。
代金は、一棹十万円なり。
この人たちは、削りの技術があるだけで、目はきかない。
所有者に「この箪笥はいくらくらいの値がありますかね」 と聞かれると、
わからないのに、
「安く見積もっても五十万円や六十万円はするでしょう」と答える。
長年商売をしているものから見れば、
十万円もしない箪笥もあるが、高く言っておけば客も満足だし、
十万円は儲かるといった寸法。
こうした商売も、隙間産業の中にはいるかもしれない。
ちゃんとした職人さんが不足・・・と思ったら、相徳に限ってさにあらず。
志望者が増えているということだ。
たんすは長持ちするので、製造者の手応えを感じるというのが理由らしい。
仕事の記録を実物として残したいという願望は、誰でも持っている。
その願望を、シンプルな桐たんすに・・・というところは、
まだ日本人は捨てたものではない。
ただし25歳ぐらいまでが限度だそうだ。
年をとると修行は難しい。
少年老い易く、修行なり難しである。
相徳は福島県会津に製造工場を持っている。
地元の労力を使う。会津は桐の産地である。地元に密着している。
(文・ もりた・なるお)
老舗風土記 産経新聞 平成3年 1991年 6月22日 ★

たんすにしてそうですが
現在は 職人になりたいという希望者が非常に多くなっています。
相徳が関係している 伝統工芸においても家具関連でも同様です。
桐たんすを作りたいとか なにをしたいという明確な希望なしに
家具を作りたいとか 伝統工芸の職人になりたいという希望については
ほとんどお引取り願うこととなります。
職人の世界は それぞれの職種仕事が 独立して特殊なものです。
また それぞれが自分のところは人とは違うを売りにしている世界です。
その中に 予備知識なしに 飛び込んでこようというのは
度胸がよすぎるように思えます。
教える側からすれば 途中で放り出されるようなことでは
今まで教えたのはなんだったんだということになります。
教えはじめる前から その覚悟を充分に確認しなければなりません。
メールでの問合せも数多くあります。
かなり厳しい調子で お受けし難い旨をお返事しますが
それでもといってくる人は皆無に近く
礼状をくれる人さえも少ないのが現状です。
ooo